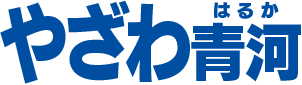やざわ こんにちは。戸田の会のやざわ青河です。通告に従い、一般質問を行います。
件名1、産前産後ケアについて。
産後ケアについては、ほかの議員も何人か取り上げておりますが、私も、2019年の12月に産後ケア事業が自治体の努力義務になったことを受け、産婦人科や助産師の先生方、現役のお母さんなどからお話をお伺いし、2020年に一般質問させていただきました。その後、戸田市においても、福祉保健センターを中心に、全妊婦面談の実施や訪問型のサービスを始めるなど、産後ケアを推進していただき、誠にありがとうございます。
今回は、国のほうでまた新たな動きがあり、産後ケアが大きく推進される時期となりましたので、改めて質問させていただきたいと思います。
まず初めに、今回の私の課題を皆様に共有していただくため、産後ケアについての概要や課題などを御説明いたします。
早速ですが、参考資料の1ページ、①産後ケアの概要を御覧ください。まず、国が進めている産後ケアには、主に3つの種類があります。1つ目が、宿泊型です。お母さんの休養だけではなく、病院や助産師などで出産後、お母さんと乳児が延泊し、帰宅後、家庭でスムーズな育児ができるよう、授乳や沐浴、寝かしつけなどの育児指導を受けることができます。
2つ目が、日帰り型のサービスです。1人から集団で一時的に来所して利用するデイサービス型のサービスであり、一、二時間程度の短いものから、6時間から7時間などの長めのものまで様々な形態がございます。
3つ目が、訪問型です。直接助産師さんなどが利用者のお宅に訪問して、育児相談や指導、家事支援などを行います。昨年から戸田市でも、この訪問型の支援を助産院さんへの委託により開始しました。
続きまして、参考資料の産後ケアの課題、対象者を絞った自治体の産後ケアの限界を御覧ください。実は先ほど説明しました国の主導する産後ケアは、高齢出産、外国人、精神疾患や育児不安、家族からの支援がない方など、ハイリスクの方や心身に不安のある妊産婦さんなどに特化しており、それ以外の多くの産婦向けの産後ケアは想定されていないのが現状でございます。また、出産後の訪問相談にはタイムラグがあるため、ハイリスクの方の特定は出産前の面談などが主になり、産後に心身の調子を崩してしまう方の中には、漏れてしまうケースもございます。
産後のお母さんの体は全治数週間の交通事故にも例えられ、全身の痛み、女性ホルモンの変化による慢性疲労や貧血、目まい、不眠、育児疲れによる肩凝りや腰痛、睡眠不足、育児不安など、誰もが心身ともに疲弊してしまいます。アメリカの産婦人科学会、ACOGの声明でも、産後早期からの継続的な産後ケアを推奨しており、それにより産後の鬱病を予防できる可能性を示唆しており、産後ケアは全産婦に必要な事業となっております。
ここで、近年の産後ケアにおける国や自治体の動きを確認いたします。
参考資料を御覧ください。2017年には、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を一体的に提供するため、子育て世代包括支援センターの設置が各市町村の努力義務となりました。2019年には、母子保健法の一部改正で、産後1年以内の母子への産後ケアが法制化され、産後ケア事業の実施も市町村の努力義務となり、昨年、2022年、戸田市で訪問型の産後ケアが開始されました。そして、今年、2023年6月30日付の自治体通知で、国から全産婦が産後ケアを利用できる旨の通知が出されました。これにより、育児不安や心身の不調がある場合に限らず、誰でも産後ケアを受けられるようになり、今後は各自治体で全産婦向けの産後ケア事業が推進し、こども家庭庁の目標である2025年までには全市区町村で産後ケアが受けられる体制の整備を進められております。
通知の内容については、参考資料の一番下の黒枠内に記載しております。国の実施要綱では、これまで対象を心身の不調または育児不安などがある者、特に支援が必要と認められる者としておりました。この国の要綱に基づき、これまで自治体によっては、独自基準を設けて産後ケアの必要性を判断し、対象者を絞り込んだりしたため、この基準によって利用をためらう女性もおりました。
今回、この国の実施要綱が産後ケアを必要とする者と改定され、希望者全員が対象になることが明確にされ、自治体による利用料の補助、全産婦へ産後ケアの利用促進が始まります。支援を必要とする人は誰でも受けられるようにして、利用を促すこと、全員を料金補助の対象とし、1回当たり2,500円を5回まで支援することなどが盛り込まれております。このように、今後は、自治体の産後ケアの対象がハイリスク産婦から全産婦へ大幅に拡大いたします。しかしながら、今の自治体の産後ケア事業では、受皿が圧倒的に足りないのが現状です。
現在産後ケアがさらに大きく動き出そうとしておりますが、まず初めに、(1)戸田市の産前産後ケアの現状と課題についてお伺いいたします。
やざわ ありがとうございました。全妊婦面談、伴走型支援として、妊婦アンケートの実施、また、助産師による訪問型の産後ケアなどを開始したとのこと、そして、今後の全妊産婦向けの産後ケアについては、サービスの人員や提供体制に課題があるなどといったお答えをいただき、同じ課題を共有していただけるものと感じております。
先ほどもお話ししましたが、これまではハイリスクの産婦さんにしか提供していなかったサービスを今後は全産婦さんへ提供しなければならず、これまでどおりの自治体の事業では受皿が圧倒的に足りないのが明らかでございます。一方で、産後ケアについては、全国の各自治体で同時にスタートしたこともあり、どこも試行錯誤しており、参考となる先進事例も少ない状況です。このような状況の中、今回、全妊婦向けの産後ケア提供体制、人員や受皿の確保について、以前お話を伺った産婦人科や助産師の先生方と協議をいたしました。その中で、やはり自治体単独で行うのは困難であり、利用期間をはじめ、民間やNPO、地域の方との連携が要となる産後ケアを提供するための官民連携のコンソーシアムの設立が必要だとの案がまとまりました。
参考資料の2ページの②を御覧ください。コンソーシアムとは、一つのサービスを提供するために連携する協議体、協議会のことです。行政と医師会や助産師会、産婦人科、助産院、当事者の方やヘルパーなどの民間事業者、ファミリー・サポートなどを行っている社会福祉協議会、そのほかのNPOや地域の方などがコンソーシアム、協議体を設立し、ハイリスク向け、全妊産婦向けの産後ケアサービスを提供する体制を構築することが望ましいと考えております。この協議体では、各団体に届く妊産婦の幅広いニーズを捉えた多様な支援メニューの協議、実際の症例や相談、要望などの情報共有、相談先や情報提供の一元化により、きめ細かく漏れのない産後ケアサポート体制の構築、また、PDCAサイクルを回し、各種事業などの評価、改善、何より全妊産婦への人員やサービスの提供体制の確保が行えると考えます。
少し形は違いますが、石川県の加賀市では、助産師連絡会を通じた支援の検討を行っており、月に一度会議を開催し、産後ケアや乳児家庭全戸訪問、また、市内産科医療機関の助産師さん、管轄の保健所、保健師さんや産前産後ヘルパーを委託しているNPO法人、市の担当職員、子育て応援ステーションの保健師、助産師、要保護児童対策地域協議会の相談員など、地域の支援者が集まり、支援が必要と考えられる妊産婦と乳児をピックアップし、母子健康手帳交付時の面談や乳児家庭全戸訪問などを通じて把握した妊産婦と乳児の情報共有を行い、それらの事例について支援方針や事業の必要性を検討する形で進行し、役割分担を行っているようです。
このように、今後の産後ケア提供体制には関係団体による官民連携協議会やコンソーシアムの設立が必要と考えますが、市の今後のお考えについてお伺いいたします。
やざわ ありがとうございました。
続きまして、妊産婦のニーズを捉えた産後ケアのメニューについて再質問を行います。
参考資料の③産後ケアのメニューの例を御覧ください。御説明したとおり、国の産後ケアは、主に宿泊型、デイサービス型、訪問型の3つの種類がございます。これを受け、各自治体で支援メニューを用意しておりますが、こういった充実したメニューだけでは今後の全産婦支援には対応し切れません。気軽にできるオンライン相談やスポットの家事支援、弁当配達など軽微なものも含めて、妊産婦さんのニーズを捉えた幅広く使いやすいメニューが必要ですが、正直、そういったお母さん方が使いたい、欲しいメニューを出し切れていないのが現状かと思います。お母さん一人一人、欲しいメニューは異なりますし、受益者負担の考え方も、使いやすければ、お金を払ってでも利用したいという方も多くいらっしゃいます。こういったきめ細やかなメニューの提案や提供は、自治体単独では困難であり、民間やNPOなどとの連携が不可欠です。先ほどお話ししましたコンソーシアムで協議して、支援メニューを検討することがやはり望ましいと考えております。
具体的なメニューといたしましては、国の主導する宿泊デイサービス型の支援。特に宿泊型は、周辺のさいたま市、川口市、蕨市で既に開始しております。また、助産師さんのサポートはもちろんのこと、ヘルパーなどにより、家事支援や調理補助、弁当配達などでお母さんの育児負担を減らす取組も効果的です。また、かかりつけ医のように、一人一人を診てくれるマイ助産師を推進するため、助産師による1年間の産後ケアサポートに対する補助を行っている自治体もございます。また、最近では、インスタなどのSNSを参考に育児を行う方も多くいらっしゃいますが、間違った子育ての情報もあり、相談をした先生から危険性についてのお話もお伺いいたしました。これらについては、ちょっとしたことでも気軽に助産師さんなどに相談できるオンラインやLINE相談、簡単登録で、いつでも利用したいときに書き込め、連絡して正しい知識を得られる体制があれば、改善されるかと思います。また、おじいちゃん、おばあちゃんなどの育児教室じじばば学級や、産後ケア版のファミリー・サポート、ママサポーターなどで周りのサポーターを増やす取組。そのほかにも、細かいところではございますが、空いた時間に参加できるパパママ学級について、会場とオンラインによるハイブリッド開催を行うなど、ほかにも参考にしておりますNPO法人のさいママさんのURリンクを貼り付けておりますので、ぜひ御覧いただけたらと思います。
産後ケアのメニューは、人それぞれ、本当にニーズが異なります。最近では、会社から家事代行などの産後ケアの補助もあったりします。しかし、逆に、里帰り出産などで地方に行き、ヘルパーなどに依頼すると、他人に子供を任せて甘えていると見られてしまいそうということで、周りの目を気にして利用を控えてしまう方もいるというお話も伺います。そういった考えを払拭し、誰もが当たり前に利用できるよう、環境や啓発も必要と考えております。そして何より、それらの情報がお母さん方に届かなければ、何の意味もございません。兵庫県の神戸市などでは、インスタグラムのインフルエンサーを活用した産後ケアの情報発信なども行っておりますが、ターゲットに合わせた周知も重要です。
そこで、産後ケアのメニューの充実や相談しやすい体制づくりについて、今後の市のお考えをお伺いいたします。
やざわ ありがとうございました。ニーズに沿った産後ケアメニューの充実をよろしくお願いいたします。
続きまして、産後ケアの制度やサービスの利用のしやすさについて質問いたします。
参考資料を御覧ください。こちらは、戸田市で昨年から開始した、④番についてですが、訪問型の産後ケア事業のパンフレットです。訪問型産後ケア事業の利用者は、先ほどの答弁で、13か月で47名、1人につき平均三、四回とありました。しかし、利用するためには、事前の登録が必要となります。また、利用は出産後1年以内であり、現在では、登録も出産後にしかできません。出産し、心身ともに疲弊している大変な中、福祉保健センターに相談をして、利用申請を提出、その後、利用決定通知書が届き、その後に事業所に連絡して、日程調整を行うという流れです。申請から利用開始まで二、三週間以上かかることもあり、勝手が分からなく、大変な時期に利用できない制度の仕組みは簡略していかなければならないと感じております。少しでも制度の利便性を利用者ファーストに近づける必要があると感じております。
昨年の12月に、当会派の宮内議員も、一時保育の質問でオンライン予約システムについて提案をしておりましたが、やはり今のお母さん方がふだん利用しているスマホやLINEなどから予約が完結できるシステムの導入なども、今後は検討していく必要があるかと考えております。
そこで、制度の利便性や利用しやすさの向上に対する今後の市の取組についてお伺いいたします。
やざわ ありがとうございました。
少しかぶる部分もございますが、今後の全産婦支援においては、マンパワーや支援の受皿を確保するためには、民間だけではなく、NPO法人や地域の方々の協力が必要不可欠だと感じております。今回相談した産婦人科や助産師の先生からも、マンパワーや人員の確保も方法次第でやりようがあるとのお話を伺いました。助産師さんや、資格を持っている潜在助産師さんの中には、産後ケアをやってみたい方が多くいるそうです。また、地域の方や高齢者などとのマッチングにより、お母さん方の負担軽減を進めている事例もあるそうです。そのほかには、子育て支援機構や助産師会などの専門団体による個人、団体向けの産後ケアセミナーなども開催しており、参入を促進する事例もございます。何にせよ、産後ケアについては、戸田市と関係団体が連携し、NPO法人などの事業者が参入しやすい体制づくりが必要と考えますが、市のお考えをお伺いいたします。
やざわ ありがとうございました。医療機関と助産師などとの協力は不可欠であると認識されていることから、NPO法人などを含め、連携協力体制を検討いただけるとのこと、よろしくお願いいたします。
今回の質問では、全産婦に向けた産後ケアの提供体制を構築するための産後ケアコンソーシアムの設立、また、民間やNPO法人など関係各所との連携体制の強化、そして、利用する産婦さんファーストの支援メニューの充実や利便性の向上を質問させていただきました。国が音頭を取り、全国一斉に始まった状況で、参考事例が乏しく、制度や仕組みづくりが難しい状況ではございますが、担当課の皆様も大変前向きに取り組んでいただいていると感じております。今後の産後ケアの充実を、改めてお願い申し上げまして、私の一般質問を終了させていただきます。