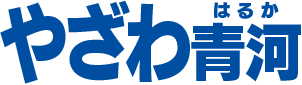やざわ 続きまして、件名2、行政評価について。
行政の業務内容を評価し、業務手法の改善を判断する行政評価ですが、その導入目的として次のような効果が期待されます。成果重視の効率的な行政運営につなげること、1つ、外部評価の実施による客観性の確保ができること、1つ、職員の意識改革、政策立案能力の向上ができること、1つ、市民に対する説明責任、理解促進が促せること。これらは、成果を上げたもの、そうでなかったものなど多々あり、特に予算の削減という意味では十分な成果を上げられない部分もあり、それをもって行政評価不要論や、いわゆる評価疲れの要因となったことも少なからずございます。今では考えられないことですが、日本における行政評価制度導入以前の1980年、1990年代では成果や効果という概念が極めて希薄であり、高度経済成長を前提とした計画や施策の見直しや廃止の議論が求められていました。そういった背景から始まった行政評価、戸田市においては2006年に導入して17年が経過しました。施策における成果と効果など職員の意識改革に大きくこれまで寄与しておりますが、後に説明する行政評価の課題もあるため、今の時代に合わせた最適化が必要な時期に来ているかと思います。
そこで、まず初めに、戸田市における行政評価の導入した経緯や現状についてお伺いいたします。
やざわ ありがとうございました。
早速ですが、参考資料2ページの②一般的な行政評価の課題を御覧ください。まず1つ、評価の仕組みについては、課題として、目的が明確化されていない、指標設定の難しさがある、事業の実施と評価の時間差があり、予算にひもづけられない、その対応策として、予算編成や総合計画の策定、運用との連携があるほか、定期評価以外の検証、数年ごと業務棚卸しなどの定期的な精査を行うことなどがございます。
次に、職員の意識については、評価自体が目的となり、事業見直しに活用されないこと、評価が形骸化され、政策形成能力の向上につながらないことなどの課題がございます。これに対しては、課長、部長、首長などの積極的な活用が重要、評価結果に基づく改善、見直しを全所管部門に徹底するなどがございます。
最後に、作業の負担については、評価に適さない事業、毎年度繰り返しの事業、細かい評価により作業件数が増加していることなどが課題に上げられるほか、職員の評価作業の負担も他自治体で多くの声がございます。こういったものについては、省力化ツールや関連事業を共有できる仕組み、また、評価の対象や項目のサイクルなどの最適化というのが必要となってくるかと思います。
このような行政評価の課題がございます。表の下に記載しておりますが、戸田市は不交付団体であり、他自治体では大きな制限となる予算の地方交付税による制限が少ないという特徴がございます。家庭に例えるなら、生活費の不安が少ない分、一般的な家庭よりも日々の生活や質における工夫、節約の意識が低くなる危険があり、生活におけるコスト意識や見直しは自主的に行わなければならないと考えております。必要に迫られなければ、何かしらのきっかけがなければ10年、20年たってもいつまでも現状維持のままになりかねません。現状評価を予算や事業、政策へと積極的に活用することや、時代や最新の技術に合わせて日々の業務を見直すことを促す意識醸成や仕組みづくり、また、それを行うための職員の時間や機会の確保が他自治体よりも必要だと感じております。
そこで、幾つか他自治体の事例を紹介させていただきます。
まず、豊田市では、行政評価を総合計画に位置づけ、予算査定への連動を強化、各部局の負担軽減とともに、評価制度の実効性を高める、また、施策評価の結果に基づかない新規事業や既存事業の拡充は原則認めないこととしております。特に行政評価と人事評価を連携し、トップ層の関心を高めるような取組を行っております。
次に、尼崎市では、年度当初、全局の管理職、課長級以上及び各部局の企画管理課施策評価担当者を対象に施策評価の研修を実施、職員の意識醸成、重要性理解を促進しております。
続きまして、大野城市では、フルコスト計算書診断、補助金等サービスチェック初期診断、業務システム最適化診断など、様々なチェックを実施しております。また、予算制度と連動した評価システムに外部評価を3年に1回全ての経常経費事業を対象に実施し、毎年度、係長級職員、若手職員を対象に集合型研修を実施、自らが第三者評価となるロールプレイ型やワークショップ型の実践的な研修を行っております。
次に、神戸市では、行政サービス改善検証委員、市における規制や手続などが事業者、団体にとって過度な負担となっていないか、合理的、多角的な検証を実施、入札契約や指定管理者制度、開発許可、補助金の4テーマで所管課及び民間事業者へのヒアリングなどの検証を実施しております。また、補助金見直しガイドラインは、ほかの自治体の多くで取り入れられておりますが、補助金の適正化を図るため、全庁的な見直しの統一基準を策定し、定期的な検証を行っております。
神戸市の事例は、毎年度の行政評価とは別に、テーマに合わせた検証を進めた事例となります。行政評価が毎年度の定期健診だとすると、数年ごとに行う各部位の精密検査のようなものと考えます。そのほかにも、資料にはありませんが、業務の見直しの気づきや腹落ちを促す事例として、長野県の塩尻市や島根県の益田市では、窓口利用体験調査として、5人家族の想定で実際に職員が窓口手続を体験し、理想の窓口をワーキングチームで考えるなどもございます。
このように、戸田市が行政評価を導入してから17年が経過しておりますが、第5次総合振興計画などの計画に合わせて評価手法などの見直しを図っているのでしょうか、お伺いいたします。
やざわ ありがとうございました。今回の第5次総合振興計画に合わせて行政評価も大幅に変更を加えているとのことでした。特に総合振興計画との連動、施策評価における企画財政部とのチェックなどは大変大きな変更かと存じます。
令和5年4月に行われた総務省のEBPM推進協議会においても、国の政策評価制度の見直しを議論しております。それによると、政策評価は、本来は政策立案過程で自然に行われるものだが、現実には意思決定過程から遊離した作業になっていないかとの問題意識を持ち、今後の見直しでは、評価のための評価をやめ、意思決定に使える評価に変える、従来の画一的、統一的な制度運用を改め、各府省の設計の自由度を高めること、また、政策評価をより精緻に行うことが目的ではない。形式ではなく実質を重視し、創意工夫や柔軟に多様なやり方を認め、前向きな調整を後押ししていくこととしております。
何にせよ行政評価で一番重要な点は、実際に施策を進める職員や意思決定を行う部長、課長などが行政評価を見直しの機会として積極的に活用していただくことでございます。せめて10年に一度程度は各事業や施策を担当職員が検討いただきたい、また、職員が創意工夫や前向きな調整を行えるよう、業務負担の軽減や人事評価などで後押しするといったことも進めていきたいと感じております。
以上、今後の要望とさせていただきまして、私の一般質問を終わらせていただきます。