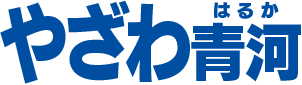やざわ おはようございます。戸田の会のやざわです。通告に従い、一般質問を行います。
件名1、ICTについて。
少子高齢化等の深刻な社会課題を抱える日本において、生産性を向上させ、経済再生を図るには、デジタルを最大限に活用することが必要不可欠です。さらに、コロナ禍によって社会全体がICTの活用がますます重要となり、デジタル化に向けた取組が加速しております。
そして、日本のデジタル社会の基盤をなすものがマイナンバー制度です。このマイナンバーカードを普及するため、国は2020年9月からマイナポイント事業を開始し、戸田市も地道な啓発活動を続けていただきました。その結果、戸田市のマイナンバーの交付率は、マイナポイント開始前の2016年6月時点では19.2%でしたが、今年2022年6月時点で47.7%と、約2.5倍まで激増しました。とはいえ、最近では少し交付数も伸び悩んでおり、現在の普及率は半分にも満たないため、今年度中にほぼ全ての国民に普及させるという国の目標を達成することは困難な状況です。
しかしながら、なぜマイナンバーカードが普及されないのでしょうか。答えは簡単です。ふだん使いできないからだと私は考えております。実際、私自身、カードを取得してから数年たちますが、住民票のため一、二回使用したことしかございません。日常的に見て、カード自体に利便性やお得感を感じませんし、カード自体なくても困りません。商品に魅力がないのに特典や地道な啓発など、これまでの取組だけで普及するのには限界があるのは当たり前で、財務省も昨年10月の分科会で、マイナポイント事業によるカードの普及効果に限界があり、自治体でのポイント付与や特典に頼らない取組を促しております。
今後の普及には、マイナンバーカード自体を魅力あるものにするため、利活用を広げ、市民にとって日常的に必要なカードにすることが重要であり、2021年9月に設立されたデジタル庁の主要な政策としてもマイナンバー制度の拡充やマイナンバーカードの利用範囲拡大が上げられております。
参考資料の1ページを御覧ください。今回の参考資料ですが、タブレットやパソコンで見ている方は下線の引かれた青い文字の部分を押していただくと参照元のリンクに飛ぶようになっておりますので、詳しく知りたい方はリンク先を御参照ください。
それでは、まず①マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載などに関する検討会資料を御覧ください。こちらに記載されているとおり、今後マイナンバーカードの機能がスマホに搭載されることになり、様々な行政手続、健康保険などの資格確認、さらには民間サービスへ活用できる環境構築が進められます。今年度中にはアンドロイドへの搭載、アイフォンについても早期の搭載を目指す予定でございます。さらにマイナンバーカードの利活用を広げるため、昨年健康保険証としての利用が開始され、2024年度末には免許証との一体化を目指す予定です。
戸田市はスマート申請をいち早く導入していただいておりますが、証明書の発行などは頻繁に行うものでもないため、日常よく使う母子健康手帳や健康保険証、免許証、民間サービスなどの活用、また参考資料②のように北九州市実証実験のような図書館アプリなど日常的に利活用できるカードを目指していただきたいと考えております。
さらに、参考資料の③のように、マイナンバーカードを活用したコンビニ等での証明書発行手数料を減額している自治体も多くございます。足立区や加古川市では手数料半額、入間市では1年間一律10円、草加市では2年間一律100円としております。こういった取組を戸田市においても減額することで、例えば窓口の横の自動交付機に減額を行っている旨のポスターを貼ることで目に見てマイナンバーのお得感や利便性を感じさせ、交付率アップや窓口の負担軽減などの効果が期待されます。このように、他自治体においてマイナンバーのさらなる利活用を進めております。
また、詳しくは再質問にてお伺いいたしますが、検針員の巡回業務の削減のため、水道などの流量データを遠隔送信可能なスマートメーター活用の実証実験を行っている自治体もございます。多様な分野においてICTの活用が進められておりますが、本市のICTに関する取組についてお伺いいたします。
やざわ ありがとうございました。
マイナンバーの利活用は、今後、急速に拡大していくことと思いますので、積極的な機能の導入を行い、日常的にふだん使い可能な魅力あるマイナンバーカードやスマホアプリとなるよう、よろしくお願いいたします。
続きまして、水道事業におけるスマートメーターの導入について再質問いたします。
電気やガス、水道などの使用量を遠隔で把握できるスマートメーターは、現在、電気については、普及率は約9割と進んでおり、水道事業においては導入のため、幾つもの自治体で実証実験が進められております。
国も水道のDXの推進を提言しており、検針の自動化による業務の効率化や検針員不足、また誤った記載など誤検針の解消、漏水の削減などのメリットがございます。
一方で、導入を阻害する要因として、通常のメーターより高額で約10倍の費用がかかるため予算不足になることや、保守的な事業運営による新技術導入への抵抗などが上げられます。
しかしながら、スマートメーター導入によるメリットは、コスト削減や効率化だけではございません。参考資料2ページの④水道などのスマートメーターを御覧ください。掛川市では、水道、ガスのスマートメーターにより、高齢者世帯のリアルタイムな水道使用状況を確認することで、通常と異なる水道の使用量を検知すると掛川市にメールが自動送信され、必要に応じて安否確認や保証人へ連絡を行う仕組みの実証実験を行っております。そのほかにも、愛知県の大府市では、水道使用量などの生活データを活用したフレイル検知実証実験なども行っております。
このように、水道事業においてもスマートメーターなど多様なICTの活用が進められておりますが、本市の取組についてお伺いいたします。
やざわ ありがとうございました。導入に向けた課題も多いものが現状ということでした。2025年度末を目標とした自治体システムの標準化をはじめ、自治体DXはこれから5年間で急速に進むことと思います。このデジタル化の変革、過渡期を乗り切れるよう、各分野における積極的なICTの活用をお願いいたします。