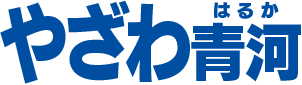やざわ おはようございます。戸田の会のやざわ青河です。通告に従いまして一般質問を行います。
件名1、公共調達について、(1)近年、国や地方自治体では、一般競争入札に移行する動きが加速しております。本市においても、順次移行が進められている状況でございますが、入札の実施状況と今後についてお伺いいたします。
やざわ ありがとうございました。ここで、簡単に一般競争入札と指名競争について説明いたします。
まず、一般競争入札は、基本的に誰もが参加できる入札方式です。戸田市では埼玉県の電子入札システムの利用により入札情報を公告して、参加事業者を募り、自ら入札に参加した事業者同士で競争して契約者を決めます。公告が必要な分、指名競争入札と比較して契約締結に長期間を要し、手続が煩雑です。また、電子入札システムに対応できない小規模事業者が漏れてしまうなどのデメリットがございます。
一方、指名競争入札は、市で登録している入札参加資格事業者の中から能力や信用などを基に市が指名した事業者が入札の参加者となり、競争して契約者を決める方式です。物品や委託などの種類や金額により1者以上または10者以上と指名業者の最低数などを定めていますが、事業者は市から指名された後に入札情報を確認し、参加しない場合は辞退という扱いになるため、一般競争よりも辞退が多い傾向にあります。
さて、この指名競争入札を中心にここ3年間の戸田市の入札結果を調査したところ、物品では9.2%程度、委託では44.5%程度が辞退などにより結果的に1者入札となっております。一般競争入札と指名競争入札における1者入札についての市のお考えをお伺いいたします。
やざわ 1者入札について原則中止を行っている他自治体の中には、不調の発生率が増加するなどの弊害により撤回したなどの事例もあり、致し方ない部分もあるかと存じます。しかしながら、入札の仕様や公募期間、公告の周知方法、指名の選定や業者など、いずれかの要因に問題があるケースも多々あり、1者入札を有効として扱うにしても、改善や見直しは適宜図っていかなければなりません。
ここ最近の1者入札を見ると、物品の中では、災害用受信機や可搬ポンプ、救急車両、ソフトウエアなど特殊な用途のものや、一時的に供給が少なかったコロナ消毒液など、ある程度理解できるものがございます。そういったもののほか、机や椅子などの備品の大量発注なども1者入札が多く見られ、市の登録業者の中に対応できるところが少ないことや、幅広い事業者への公告がうまくできないことなどが原因であるように感じております。次に、委託については、システム関係や印刷、封入業務、庁用自動車、防災、防犯設備、臨時職員やサポートスタッフ、期間的なイベントなど、1者入札となっております。地理的な条件や特殊なものが多い一方で、数年間続いているものもあり、場合によっては例年同様の事業の入札が続くことで、参加事業者や入札価格などが推測しやすくなり、あらかじめ競争に勝てないと判断し、辞退していることも要因の一つかと考えられます。このような1者入札にならないため、市ではどのような取組をしているのかお伺いいたします。
やざわ 指名競争入札は、市が指名を行うため、結果的に1者になるのは、市の選定に改善の余地があるとも考えております。先ほどいただいた答弁は、主に担当課や仕様書の精査についてでしたが、それ以外にも1者入札の原因として対応できる事業者の確保や公告における周知などの課題も上げられます。事業者の入替えや指名業者数を増やすこと、登録事業者や公告先を増やすため、埼玉県の電子入札システムと戸田市の登録業者を同時に活用した公募型の指名入札なども可能かもしれません。工夫の余地はまだまだあるかと思いますし、何年も1者入札が続くことを避けるためにも積極的な対策をよろしくお願いいたします。
さて、続きまして、再質問を行います。コロナ禍において入札会場へ直接足を運びづらい状況がありますが、入札の円滑化や競争の確保についてコロナ禍における市の対策をお伺いいたします。
やざわ コロナ禍において、郵便入札の導入により前日までに辞退の状況が分かるため、新たな事業者を指名しての再入札となり、結果的に1者入札が減少しているとのことは喜ばしいことでございますが、市の3年間の入札結果を見ると、2者入札までを含めると全体の13から14%に上ります。また、再入札の手間などを考えると、1者ないし2者入札の根本的な改善が必要かと考えております。そういったこともあり、最後に幾つか提案と要望を行いたいと思います。
まず1つ目として、入札結果のデータベース化です。現在の戸田市の入札結果は、一、二枚のページに一つの入札情報をまとめる形で保存しております。一方、和光市や栃木市などでは、エクセルのように1行に1件の入札情報がまとめられております。これにより、件名や種別、担当課ごとの入札情報が簡単に抽出することが可能となり、見直しや再入札時に活用できると考えます。
次に、2つ目として、入札の横断検索サイトの活用です。既に活用されている方などもいらっしゃるかもしれませんが、国内最大手の入札情報サイトNJSSの姉妹サイト調達インフォというサービスがあります。調達インフォは、自治体の調達担当者向けに過去10年間、約1,300万件、全国のあらゆる入札、落札データの入札案件、落札情報を無料で閲覧できるサービスで、先月から自治体担当者向けに各種工事案件の部署別の調査資料の提供や参考仕様書の調査代行サービスを開始いたしました。これを利用することで、新しい事業を行う際に他自治体の類似した仕様書を確認したり、現事業の比較なども行え、各担当課での活用も考えられます。また、民間の入札大手と連携することで、民間への入札情報の提供などにつながるかもしれません。
最後に、不調や1者入札などの原因究明とフィードバックです。特に長年少数の入札になっている事業などについて、事業者の辞退理由について把握し、発注時期が悪いのか、仕様内容が悪いのか、比較要件が厳しいのか、事業者の範囲や選定、周知など、見直しの余地はないかなど、事後にフィードバックを行う必要があると考えます。
以上、提案と要望を申し上げまして、件名1の公共調達について及び私の一般質問を終了いたします。