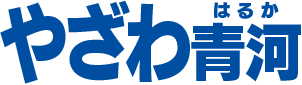やざわ 戸田の会のやざわ青河です。通告に従い、一般質問を行います。
件名1の官民連携について。
人口減少や少子高齢化社会において、民間の持つ多様なノウハウや技術を活用して限られた予算を効率的よく使い、業務効率化やサービスを向上させる官民連携を推進することは重要です。戸田市では指定管理や公民連携ファームなどにより民間ノウハウなどを活用して行政課題の解決を図っておりますが、官民連携の現状と今後についてお伺いいたします。
やざわ ありがとうございました。公民連携ファームを活用して多くの包括連携や連携事業が実現しており、大変すばらしく思います。官民連携で大切なのは誰とやるか、いかに優良な事業を発掘して結びつけるかであり、包括連携などは最初のアプローチとして重要ですので、今後とも推進をお願いいたします。
それでは、順次、再質問いたします。
全国的には包括連携の協定数は、2016年、2017年をピークに減少傾向にあります。これは包括連携協定の効果が自治体や企業とも実感できないことが原因だと考えられます。現状では企業が一方的に無償や低予算で自治体をサポートする形のものが多く、企業側がメリットを享受できず、連携が単発で終わってしまうおそれもございます。これを避け優良企業の発掘や公民連携の質をさらに高めるためにも、自治体と民間で双方が具体的に何をしてギブ・アンド・テークを成り立たせるかを突き詰めなければなりません。そのためには次の2つが重要だと考えております。1つ目は、戸田市が保有する地域資源の把握と発信、マッチングについて。2つ目は、成果型民間委託など新たな官民連携の手法の導入や効果検証や見直しについてです。
まず1つ目の戸田市が保有する地域資源の把握と発信、マッチングですが、ここで言う地域資源の把握と発信とは、市内の人、物、金、情報などを民間の視点から見直して活用しやすい形でまとめ、情報発信やマッチングを行うことです。具体的な事例として、埼玉県横瀬町のよこらぼがございます。よこらぼは、企業、団体、個人が実施したいプロジェクト、取組を実現するために、横瀬町のフィールド、資産を有効に利用し、横瀬町がサポートを行う公民連携の仕組みです。提案から実施まで一貫して民間の主導で行われ、民間の縛りが少なく自由度が極めて高い効率的なノウハウやアイデアを取りやすいのが特徴です。この仕組みでは基本的に補助金を必要とせず、横瀬町は主に遊休資産や職員、町民のリソース提供などのサポートに徹しており、採択の際には、提案者、町民、まちの三者それぞれにしっかりとメリットがあることを最も大切に、公民連携におけるハードルを極力下げ持続可能な地域社会をつくるために、誰一人取り残さず関わる全ての人が幸せになるプロジェクトを積極的に採択、応援するというコンセプトを持っています。
戸田市においても遊休資産やボートコース、道満、公民館などの公共施設、戸田公園駅、トビックなどの施設や場所、設備など、市内の地域資源を改めて見直し取りまとめて情報発信を行うことで、横瀬町のような民間主導の公民連携をさらに推進することが可能になると考えております。
別の事例では、全国や都道府県など広域の公民連携自治体プラットフォームの活用なども効果的です。民間が運用する自治体コネクトという公民連携マッチングプラットフォームに登録することで、全国の民間企業へ公民連携の情報発信を行えるようになります。また、大阪府では、大阪府及び府内43市町村の公民連携プラットフォームを運用しておりますが、埼玉県でも積極的にプラットフォームをつくるべきだとは考えております。
このように、現在の公民連携ファーム以外の仕組みを活用することで、さらなる情報発信と多様な民間と連携する機会が得られると考えられます。そのほかにも、横浜の財政見える化ダッシュボードなども面白い取組です。市の分野ごとの一つ一つの事業の概要や予算などの推移、事業の計画などを全てウェブで公開しており、民間は個々の事業に対する提案をワンタッチで行える仕組みを構築しております。
このように、よこらぼや自治体コネクトなど、効果を発揮している官民連携手法がございますが、今後本市ではどのように官民連携を推進していくのかお伺いいたします。
やざわ 引き続き再質問いたします。
続いて、成果型民間委託など新たな官民連携の手法の導入や効果検証、見直しの実施についてです。自治体の民間への委託には従来の仕様発注方式と性能発注方式というものがございます。前者の仕様発注方式は、担当課が作成した仕様書のとおりに民間が業務行う従来の発注であり、民間企業の創意工夫が生かしにくい傾向にあります。後者の性能発注方式とは、委託した民間企業には一定の性能を求める上で、具体的な業務運営は民間企業に任せる方式であり、民間企業の自由度が大きく、創意工夫やノウハウなどを生かしやすい委託になります。以前私が質問した包括施設管理などの委託もこの性能発注方式となります。また、最近では成果に応じた委託費を支払うソーシャル・インパクト・ボンド、SIBや、成果連動型民間委託契約方式、PFSなどの新しい手法も増えております。
現在の戸田市の公民連携や民間委託を考えると、仕様書による発注では例年どおりの発注になりやすいですし、5年、10年など長期の指定管理委託などであっても同じ事業者が引き続き業務を継続することも多く、10年の間に効率的なデジタル化やシステム、民間の新たなノウハウなどが生まれても採用されずに従来どおりの内容での指定管理となってしまわないかなど懸念しております。今後はさらに民間に任せる部分は積極的に民間へ任せ、ノウハウを活用できるような公民連携を進める必要があると考えております。指定管理の切替え時期や行政評価の効果検証時に、市が行う妥当性、民間への委託の可能性、さらなる効率化の検討を行うことが望ましいと考えておりますが、各担当課で委託方式を検討したりするようなノウハウがまだ共有されておらず、SIBなどの新しい委託方式は戸田市ではまだ導入されていないため、選択肢にも上がりづらい状況だと考えております。
伊賀市をはじめ多くの他自治体では公民連携ガイドラインを作成して公民連携や民間委託などの手法などを整理し、事業ごとに最適な手法を選べるようにフローチャートなどを掲載して、市役所全体で共有しております。また、ソーシャル・インパクト・ボンド、SIBや成果連動型民間委託契約方式、PFSなど新たな委託手法を取り入れている自治体も多くございます。本市では今後活用する考えはあるでしょうか、お伺いいたします。
やざわ 新たな委託手法について認識しているとのことでした。本来は、行政課題に対してSIBなどの新しい手法がベストであれば導入するとの手順が正常だと思います。しかしながら、担当課におけるノウハウがない現状であり戸田市でも導入実績もないため、現実的には選択肢にも上がらない可能性もございます。多様な手法で当たり前に民間委託の手法を選べるようにも、少し順序は違いますが、SIBなどの手法を導入するために最適な課題を選ぶという方法もあるかと存じます。
続きまして、地域リソースの活用について再質問いたします。
行政課題の解決に向け、官民連携においては民間などの企業以外にもボランティアや市民活動などの地域リソースの活用も重要と考えております。現在、市民活動やボランティアなどをしている方のサポートはTOMATOが中心となって行っております。その一方で、2020年の社会意識に関する世論調査によると、社会のために役立ちたいと思っている方は63.4%おり、活動している方以外にもボランティア活動に興味はあるが踏み切ることができない層も多いと思われます。そういった潜在的ボランティアとも言える方をさらに掘り起こすため、また現在のNPO団体の情報をさらに発信を行うためにも、先ほどの再質問と同様、全国的な情報サイトの活用が効果的かと考えます。
具体的な事例としては、ボランティア募集情報activoや社団法人移住・交流推進機構、JOINの地域おこし協力隊をはじめ、「さとふる」などのふるさと納税サイト、クラウドファンディングの活用なども考えられます。今後の少子高齢化社会、多様なニーズに応え持続的な社会を構築するためにも、社会貢献の醸成が重要となってまいりますが、ボランティア活動に関して、ボランティア・市民活動センターはどのような取組を行っているのでしょうか、お伺いいたします。
やざわ TOMATOに所属する各団体の活動を応援するためにも、多様な媒体での情報発信やそれらノウハウの提供などをさらに推進して、社会貢献的な官民連携を推進していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
最後に、公民連携を推進している自治体としていない自治体では、長期的に見ると大きな地域格差が生じる可能性がございます。公民連携を推進している自治体は従来の行政にはなかった地域課題解決の新しい知見を豊富に蓄積できる、一方で公民連携が進んでいない自治体では前例踏襲型で地域の問題に対処せざるを得ないことになってまいります。ぜひ戸田市においても公民連携の様々な手法を当たり前に行えるように、積極的に導入をしていただくようお願い申し上げまして、私の一般質問を終了させていただきます。